
こんにちは。
現在SIerでWebエンジニアをしながら、副業でライターとして活動しているKAITOです。
この記事では、私が「機械工学からプログラミング、そして文章の世界」へとたどり着くまでのちょっと変わった物語を語ってみようと思います。
機械工学科で育った「ネジと油の申し子」
大学では機械工学を専攻していました。
周りの友人たちは「ロボット」「エンジン」「流体力学」などに情熱を注ぐ中、私はなぜか「機械って、なんで動くんだろう」よりも、「それを動かしてる人間の考え方のほうが面白いな」と感じていました。
授業中、教授が「摩擦係数の影響を〜」と真剣に語る中、私は「この教授のプレゼン資料、フォントがやたら情熱的だな」と思っていたくらいです。
完全に“文系の皮を被った理系”でした。
しかしながら、実験でネジを締めすぎて装置を壊したときは、さすがに理系の誇りが傷つきました。
それ以来、ネジを見ると少し距離を置いてしまうのが今でも癖です。
プログラミング教室との出会い:Hello, World! が人生を変えた日
大学2年のある日、「これからはプログラミングの時代だ!」という友人の言葉に半信半疑ながら、プログラミング教室の門を叩きました。
最初の課題は「Hello, World!」を表示するだけ。
当時の私は「たった一行出すだけで何が楽しいんだ?」と思っていました。
しかし、プログラムが自分の指示どおりに動いた瞬間、頭の中に電流が走ったんです。
「おいおい、こいつちゃんと俺の言うこと聞くじゃん!」と。
その日から私の人生は、文字通り“コードまみれ”になりました。
とはいえ最初はバグの嵐。
「動け!」「なんで動かないんだ!」と怒鳴りながらも、結局原因はセミコロンの付け忘れ。
プログラミングの世界では“神様よりもセミコロンの方が偉い”という真理を学びました。
学生フリーランス時代:深夜のカフェがオフィスだった
大学3年の頃、「せっかくだから自分のスキルで誰かの役に立ちたい」と思い立ち、フリーランスのWebエンジニアとして活動を始めました。
最初の仕事は、友人の知り合いからの依頼。
「Webアプリ作れる?」
「……たぶん。」
この“たぶん”が、まさか本当に仕事になるとは思いませんでした。
とはいえ、現実は想像以上に過酷。
大学の課題と納期の板挟みになりながら、深夜のカフェでMacBookを開く毎日。
気づけばカフェイン濃度で動く人間になっていました。
当時は「眠気=敵」だったはずなのに、いま振り返ると「眠気=親友」みたいな関係性です。
バグを修正して夜明けを迎えるときの達成感は、いまでも鮮明に覚えています。
しかも、作ったアプリをクライアントが使ってくれたときの一言
「これ、めっちゃ便利だね!」
その瞬間に、「自分のコードが誰かの役に立つ」ことの喜びを知りました。
この経験が、今の仕事の原点になっています。
SIer就職:個人からチームへ、働き方のアップデート
卒業後は、より大規模な開発に携わりたいと思い、SIer企業に就職しました。
学生時代は一人で完結するプロジェクトばかりでしたが、会社ではチームで進める開発。
最初は正直戸惑いました。
「え、コードレビューって“添削”じゃなくて“儀式”なの?」と驚いたり、
「コミットメッセージに“修正した”って書くと怒られる」ことを初めて知ったり。
でも、少しずつ仲間と開発する面白さが分かってきました。
自分が苦手な部分を他のメンバーが補ってくれるし、誰かのバグを一緒に笑いながら直せる。
この“連携プレイ感”は、フリーランス時代には味わえなかったものです。
ただし、レビューコメントで「インデントがズレてるよ」と指摘されるたびに、
「1スペースの狂いに気づくあなたの視力、もはや顕微鏡レベル」と心の中で突っ込んでます。
副業ライターとしての挑戦:伝えることの楽しさに目覚める
そして現在、エンジニアとして働く傍らで、副業ライターとしても活動しています。
きっかけは、社内ドキュメントを書いていたときの同僚の一言。
「KAITOくん、文章わかりやすいね!」
その瞬間、「あれ? もしかして、文章書くの向いてるのかも?」と電流が走りました。
そこから、技術記事やWebメディアの記事執筆を始めました。
最初の頃は、1,000文字書くのに3時間かかるなんてザラ。
締め切り前になると、WordPressの投稿画面とにらめっこしながら「バグより文章が動かねえ!」と嘆いていました。
でも、読者から「分かりやすかった」「思わず笑いました」と言ってもらえるたびに、
「伝えるってこんなに面白いんだ」と感じるようになったんです。
最近では、「コードで動かす」「文章で動かす」この2つのスキルをどう融合できるかを考えています。
どちらも本質は同じ―人の心を動かす設計だからです。
技術と文章、どちらも「設計」の延長線上にある
エンジニアは機能を設計し、ライターは言葉を設計する。
どちらも相手の立場に立って、どうすれば伝わるかを考える仕事です。
たとえば、WebアプリのUIを設計するときは「このボタン、押したくなるかな?」と考えます。
記事を書くときは「この見出し、読みたくなるかな?」と考えます。
思考の構造は同じなんです。
もしかすると、機械工学で学んだ“システムを分解して理解する力”が、
文章構成にも自然に生かされているのかもしれません。
これからの目標:「わかる×笑える」技術を伝えたい
私はこれからも、エンジニアとしての技術を磨きながら、
ライターとして「難しいことを楽しく伝える力」を極めたいと思っています。
AI、IoT、Web3……技術の世界はどんどん広がっていますが、
多くの人にとってはまだまだ“難しそう”な印象があります。
私はそんな技術を、専門用語に頼らず、笑いながら理解できる形で発信していきたい。
「技術って、意外と面白いじゃん」と思ってもらえる瞬間を増やすこと。
それが、今の私の目標です。
最後にひとこと
よく「エンジニアとライター、どっちが本業なんですか?」と聞かれます。
正直どっちも本業です。どっちも好きです。
if (好きなことを仕事にできる) {
最高の人生;
} else {
コーヒーを淹れてもう一回挑戦;
}これが、私の人生を動かすコードです。
今日もどこかで、カフェの片隅でコードを書きながら、
“読まれる文章”を試行錯誤しているエンジニア兼ライター、KAITOでした。
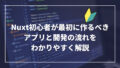
コメント